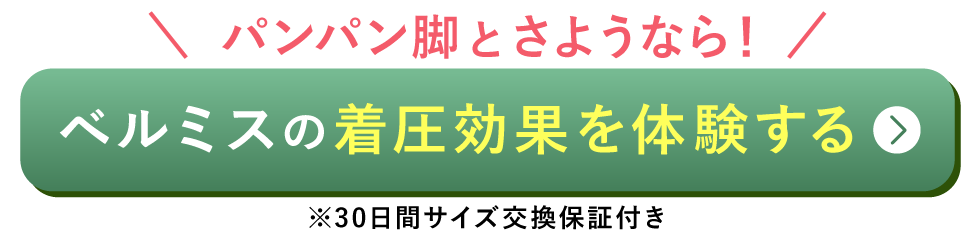「足のむくみを速攻で解消できる食べ物は?」
「夕方になると足がパンパンにむくんでつらい…」
足のむくみは、食べ物や飲み物の選び方によって、数時間から一日ほどで目に見えて軽減されることがあります。とくに、カリウムやマグネシウムを多く含む食材がむくみ解消に効果的です。
この記事では、むくみの原因と、むくみ解消に即効性が期待できる食べ物・飲み物を紹介します。また、食事以外のケア方法についても解説します。翌朝には、足の軽さを実感できるかもしれません。
目次
即効で足のむくみを取る食べ物・飲み物
足のむくみをすばやく改善するには、カリウムやマグネシウムを豊富に含む食材の摂取が有効です。ここでは、即効性が期待できる果物・野菜・飲み物などを紹介します。
果物(バナナ・キウイ・アボカドなど)

むくみの軽減には、カリウムを多く含む果物の摂取が効果的です。
以下は、特におすすめの果物とその特徴です。
- バナナ:カリウム360mg/100g
消化が良く、即効性が期待できます。 - キウイフルーツ:カリウム290mg/100g
ビタミンCも豊富で、血管の健康維持に役立ちます。 - アボカド:カリウム720mg/100g
良質な脂質を含み、栄養価の高さが特徴です。 - メロン:カリウム350mg/100g
水分が多く、利尿を促す作用があります。
なかでもバナナは、手軽に取り入れやすく、むくみ対策に適した果物です。中サイズ1本(約100g)には、カリウムが360mg含まれています。

近藤 好美
ORIENTAL GREEN
「明日までに少しでもスッキリさせたい!」というご相談をよくいただきます。そんな時におすすめしているのが、手軽なバナナやキウイなんです。難しいことを考えなくても、まずは「いつもの食事にプラス一本」から。そんな手軽さが、美しさを保つ方々の継続のコツでもありますよ。
野菜(ほうれん草・小松菜・トマトなど)

カリウムとマグネシウムは、体内の水分バランスを整える働きがあり、むくみの予防や解消に役立ちます。特に緑黄色野菜はこれらのミネラルを豊富に含んでおり、毎日の食事に取り入れることで、無理なく体調を整えることができます。
野菜ごとの栄養特性を知って選ぶことで、より効率的なケアが可能になります。
| 野菜名 | カリウム(100g) | マグネシウム(100g) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ほうれん草 | 690mg | 69mg | 鉄分も豊富、貧血改善にも |
| 小松菜 | 500mg | 12mg | カルシウムも多く骨も強化 |
| トマト | 210mg | 9mg | リコピンで血行促進 |
| きゅうり | 200mg | 15mg | 95%が水分、利尿作用抜群 |
- ほうれん草や小松菜は、軽く茹でてお浸しにすると、かさが減ってたっぷり食べやすくなります。
- トマトは加熱することで、リコピンの吸収率が3〜4倍に高まるとされています。
芋類(じゃがいも・里芋など)

芋類は炭水化物に分類されますが、実はカリウムを多く含む優れた食材でもあります。
「芋は太りやすいのでは」と心配されることもありますが、適量であればむくみの軽減に役立つ可能性が高いとされています。
- じゃがいも:カリウム410mg/100g
主食代わりにもなり、満足感が得られやすい食材です。 - 里芋:カリウム640mg/100g
ぬめり成分が胃腸にやさしく、消化を助けます。 - さつまいも:カリウム470mg/100g
食物繊維が豊富で、腸内環境の改善にもつながります。
皮ごと調理することで、カリウムの含有量が20〜30%ほど多くなるといわれています。
豆類・種実類(納豆・アーモンドなど)

豆類や種実類は、植物性たんぱく質とミネラルを同時に摂取できる栄養価の高い食材です。とくに納豆は、毎日の食事に取り入れやすく、むくみ予防に役立つ定番の食品とされています。
| 食品名 | カリウム(100g) | 主な栄養素 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 納豆 | 660mg | たんぱく質16.5g | 発酵食品で腸内環境を整える |
| アーモンド | 760mg | マグネシウム310mg | 間食向き、栄養補給に便利 |
| 枝豆 | 590mg | たんぱく質・食物繊維 | おつまみや副菜に使いやすい |
| ピスタチオ | 970mg | たんぱく質 | 少量で高ミネラルが摂れる |
納豆は、1日1パック(50g)を目安に取り入れるのが適切です。アーモンドは、1回あたり10〜15粒程度が適量とされています。
どちらも栄養価が高い食品であるため、摂りすぎには注意が必要です。過剰に摂取すると、かえって体内のバランスを崩す可能性があります。
魚類(サバ・鮭など)

魚に含まれるEPAやDHAには、血行を促進する働きがあり、むくみの改善に役立ちます。慢性的なむくみに悩んでいる方には、日常の食事に魚を取り入れることが効果的です。
- サバ:EPA・DHAが豊富で、カリウムも370mg/100g含まれています。
- 鮭:アスタキサンチンによる抗酸化作用があり、疲労や冷えの改善にも効果的とされています。
- いわし:カリウム380mg/100gに加えて、カルシウムも多く含まれており、骨の健康にも貢献します。
- あじ:比較的価格が安く、日常的に取り入れやすい魚です。
焼き魚よりも煮魚のほうが、煮汁ごと取り入れられるため、水分代謝を助ける働きが期待できます。
肉・卵・乳製品(鶏むね肉・ゆで卵・ヨーグルトなど)

良質なたんぱく質は、血液中のアルブミン濃度を高める働きがあり、体内の水分バランスを整えることで、むくみの根本的な改善につながります。
低たんぱくの状態が続いている方は、たんぱく質の摂取量を意識的に増やすだけでも、むくみの軽減を実感できるでしょう。
- 鶏むね肉:高たんぱく・低脂肪で、さまざまな調理に使いやすい食材です。
- ゆで卵:必須アミノ酸をバランスよく含み、手軽に取り入れやすい完全栄養食品です。
- ヨーグルト:乳酸菌が腸内環境を整え、消化・吸収にも良い影響を与えます。
- カッテージチーズ:脂質が少なく、高たんぱくでヘルシーな乳製品です。
たんぱく質は、体重1kgあたり1〜1.2gを目安にすると良いとされています。
飲み物(白湯・カフェイン入りのお茶・トマトジュースなど)

むくみの改善には、こまめな水分補給を心がけることが大切です。
「水分を控えたほうがよいのでは」と考えられがちですが、実際には水分をこまめに摂ることで、体内の巡りが良くなり、代謝も促進されます。
| 飲み物 | 効果 | 摂取タイミング |
|---|---|---|
| 白湯 | 内臓を温めて代謝を促進 | 起床時・食前30分前 |
| 緑茶・ウーロン茶 | カフェインによる利尿作用 | 午前中や午後の早い時間 |
| トマトジュース | カリウム260mg/100mlで水分排出をサポート | 食事と一緒に |
| ハーブティー | リラックス効果で血行を促す | 就寝前 |
水分は一度に大量に摂るのではなく、1日あたり1.5〜2リットルを目安に、数回に分けてこまめに飲むことが大切です。
\ 毎日のむくみに悩んでいませんか? /
食事と合わせて、手軽にむくみケアを始めるならベルミスがおすすめです。
むくみの原因

むくみの根本的な原因を理解することで、より効果的な対策を講じることができます。ここでは、多く見られる原因とその対処法を紹介します。
塩分の摂りすぎ
体内のナトリウム濃度が高くなると、水分をため込んでバランスをとろうとする働きが起こります。これが、むくみの主な原因のひとつです。現代の食生活では、気づかないうちに塩分の目安量(男性7.5g未満、女性6.5g未満)を大きく超えてしまっていることが多くあります。
- コンビニ弁当:約5〜8g
- ラーメン1杯:約6〜10g
- 漬物類:約2〜3g/100g
- 加工肉類:約2〜4g/100g
対策として、カリウムを多く含む食品を意識して取り入れることで、ナトリウムの排出を促進できます。また、出汁や香辛料を活用して塩分を減らしても満足できる味付けを心がけましょう。
アルコールの飲み過ぎ
アルコールには利尿作用がありますが、その一方で血管の透過性が高くなります。そのため体内の水分が漏れ出しやすくなり、むくみを引き起こす原因となります。実際に、飲酒の翌日にむくみがひどくなる方は少なくありません。
- 血管が拡張し、水分が血管外へ漏れやすくなる
- 肝機能が低下し、たんぱく質の合成量が減少する
- 脱水状態により、体が水分をため込もうとする
飲酒の際には、同量以上の水分をこまめに摂ることを心がけましょう。翌日は、カリウムを多く含む食品を意識して取り入れると、むくみの回復に役立ちます。
運動不足による血行不良
筋肉によるポンプ作用が弱まると、血液がうまく心臓に戻れず、下半身に水分がたまりやすくなります。とくに、ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、全身の血流を支える重要な役割を担っています。
デスクワーク中心の生活では、次のようなリスクが考えられます。
- 長時間同じ姿勢を続けることで、血流が滞りやすくなる
- ふくらはぎの筋力が低下し、ポンプ機能が弱まる
- 重力の影響により、下半身に血液がたまりやすくなる
デスクワークが中心の方は、1時間に1回は立ち上がり、つま先立ちやふくらはぎの軽いストレッチを行うようにしましょう。エレベーターではなく階段を使うといった小さな習慣でも、血流の改善に役立ちます。

近藤 好美
ORIENTAL GREEN
「第二の心臓」と言われるふくらはぎを意識して動かすことは、むくみケアの基本中の基本です。これまで3,000人以上のお客様のお体に触れてきましたが、デスクワークの方のふくらはぎは、ご自身が思っている以上に硬く、冷たくなっていることが多いんです。
1時間に1回、座ったまま足首を回すだけでも全然違いますから、ぜひ「お仕事の句読点」だと思って取り入れてみてください。
体の冷えによる水分代謝の低下
体温が1度下がると、基礎代謝はおよそ12%低下するといわれています。この変化によって水分代謝も滞り、むくみが起こりやすくなります。
特に女性は筋肉量が少ない傾向があるため、冷えによるむくみが目立ちやすいとされています。
- 血管が収縮し、血流が悪くなる
- 腎機能が低下し、水分の排出がうまくいかなくなる
- リンパ液の流れが滞りやすくなる
冷えを改善するには、温活が有効です。
入浴の際は、38〜40度のお湯に15〜20分ほどゆっくり浸かると、体の芯から温まりやすくなります。血流が促進され、水分の巡りも整いやすくなるため、むくみの軽減に効果が期待できます。
ホルモンバランスの乱れ
女性ホルモンの変動は、体内の水分バランスに大きな影響を与えることがあります。とくに、生理前や更年期には、ホルモンの働きによってむくみが起こりやすくなります。
- 生理前(黄体期):プロゲステロンの働きにより、水分をため込みやすくなります。
- 排卵期:エストロゲンの急激な変化により、一時的にむくみが出やすくなります。
- 更年期:ホルモン分泌が不安定になり、むくみが慢性化しやすくなります。
このような時期には、塩分の摂取を控え、カリウムを多く含む食品を意識して取り入れることが大切です。また、適度な運動を習慣にすることで、ホルモンバランスを整えやすくなります。
貧血や低たんぱく状態
血液中のアルブミン濃度が低下すると、水分を血管内に保つことが難しくなり、深刻なむくみの原因となることがあります。とくに、極端な食事制限を行っている方に多く見られる傾向です。
- 慢性的な疲労感が続く
- 髪の毛が細くなったり、抜けやすくなる
- 爪が割れやすくなる
- 朝起きても疲れが残っている
改善を目指すには、1日の摂取カロリーのうち20〜25%をたんぱく質から摂ることを意識しましょう。
病気が隠れているケースも
急にむくみが現れた場合や、片側の足だけにむくみが生じている場合には、何らかの病気が隠れている可能性があります。このようなケースでは、医療機関での検査が必要です。
- 指で押した跡がなかなか戻らない
- 左右の足でむくみの程度に明らかな差がある
- 短期間で急激に悪化する
- 息切れや動悸などを伴う
上記のような症状が見られる場合には、マッサージや食事療法で対応しようとせず、まず医師の診断を受けましょう。
食べ物以外でできるむくみケア

日常の中でできるセルフケアを食事と合わせて取り入れることで、むくみ解消に役立ちます。ここでは、むくみを和らげる方法を紹介します
軽い運動・ストレッチで血流促進
運動は、むくみを根本から改善するための最も効果的な方法のひとつです。毎朝15分ほどのストレッチを習慣にすることで、血流が促され、むくみにくい体づくりにつながります。施術の効果を持続させるためにも、日々の生活に軽い運動を取り入れてみましょう。
むくみの軽減に効果的なエクササイズ:
- ふくらはぎのストレッチ:壁に手をつき、片足を後ろに引いて15秒キープ
- 足首回し:時計回り・反時計回りに各10回ずつ
- つま先立ち:30秒間キープを3セット
- 足上げ:仰向けになり、壁に足をつけて10〜15分間キープ
これらのエクササイズは、朝起きてすぐや夜寝る前に行うと、翌朝の足の軽さを感じやすくなります。毎日のルーティンに取り入れることで、無理なくむくみの予防が続けられます。
お風呂・温活で体を芯から温める
入浴は、血行を促しながら心身をリラックスさせる、むくみ対策に効果的なセルフケアのひとつです。体がしっかり温まることで、巡りが良くなり、水分代謝のサポートにもつながります。
| 入浴方法 | 温度 | 時間 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 全身浴 | 38〜40℃ | 15〜20分 | 全身の血流を促進する |
| 半身浴 | 37〜38℃ | 20〜30分 | 心臓への負担を抑えながら温まる |
| 足湯 | 40〜42℃ | 10〜15分 | 下半身の血流を集中的に促す |
| 温冷交代浴 | 40℃⇔水 | 3分×3回 | 血管の収縮・拡張で循環を活性化する |
入浴時には、入浴剤を活用するのもおすすめです。入浴剤を使うことで、リラックス効果が高まり、入浴による温め効果も持続しやすくなります。好みの香りを選べば、気分転換にもつながります。

近藤 好美
ORIENTAL GREEN
お風呂で体を芯から温めるのは、私たちがインディバの施術で目指していることと全く同じアプローチです。体が温まり血の巡りが良くなった後は、まさにむくみケアの「ゴールデンタイム」。このタイミングで軽いストレッチやマッサージを加えると、相乗効果で驚くほど足が軽くなりますよ。ぜひ5分でもいいので、ご自身の足をいたわる習慣をつけてみてくださいね。
着圧レギンスで効率的にむくみ対策
足のむくみ対策には、着圧レギンスの使用もおすすめです。
ベルミスの着圧レギンスは、足首から太ももにかけて段階的に圧力がかかり、血流を促すことでむくみの軽減が期待できます。医療用着圧ストッキングと同様に、足首に最も強い圧がかかり、上に向かって徐々に弱まるよう設計されています。
- 段階着圧設計により血流を促す
足首から太ももにかけて圧力が徐々に弱まる構造で、滞った血液やリンパの流れをスムーズにします。 - 着圧によるポンプ作用のサポート
筋肉の代わりに圧をかけることで、第二の心臓ともいわれるふくらはぎの働きを補います。 - 長時間の座り仕事や立ち仕事にも対応
履いているだけで脚全体を引き締め、むくみの原因となる血液や水分の滞留を防ぎます。 - 体を締めつけすぎない
適度な圧力と伸縮性により、心地よく血流をサポートできます。 - 日中・就寝時に使い分けられるシリーズ展開
生活スタイルに合わせて着用タイミングを選べるため継続しやすく、むくみ対策が習慣化しやすいです。
むくみを放置すると、脚のラインや体調にも影響します。見た目とめぐりを同時に整えたい方は、ベルミスで美脚ケアを習慣にしてみてください。
まとめ

足のむくみを即効で解消するには、カリウムやマグネシウムを多く含む食材を意識的に取り入れることが大切です。
とくに、以下のような食品を摂取するのが効果的です。
- 果物:バナナ・キウイ・アボカドなど(カリウムが豊富で即効性あり)
- 野菜:ほうれん草・小松菜・トマトなど(水分バランスの調整に役立つ)
- 芋類:じゃがいも・里芋・さつまいも(主食代わりにも◎)
- 豆類・種実類:納豆・アーモンド・枝豆・ピスタチオ(高ミネラルで間食にも適する)
- 魚類:サバ・鮭・いわし・あじ(EPA・DHAによる血行促進)
- 肉・卵・乳製品:鶏むね肉・ゆで卵・ヨーグルト(たんぱく質不足によるむくみ改善に)
- 飲み物:白湯・緑茶・トマトジュース・ハーブティー(こまめな水分補給が重要)
食事だけでなく、生活習慣の見直しもむくみ対策には効果的です。たとえば、軽い運動やストレッチを取り入れることで血流が促進され、ふくらはぎのポンプ機能をサポートできます。入浴や温活では、38〜40℃程度のお湯にゆっくり浸かることで体が芯から温まり、代謝の向上が期待できます。
また、着圧レギンスを活用するのもおすすめです。足首から太ももにかけて段階的に圧力をかけることで、血液やリンパの流れを整え、脚のライン改善にもつながります。
食事・運動・日々のケアを意識することで、むくみにくい体づくりを目指しましょう。

この記事の監修者
近藤 好美
ORIENTAL GREEN 銀座インディバ
オーナーセラピスト/インディバスーパーバイザー
セラピスト歴25年、インディバ施術歴20年以上の経験を持つ、身体のラインとコンディションを整えるプロフェッショナル。これまでに3,000人以上の身体の悩みに向き合い、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの施術を提供。